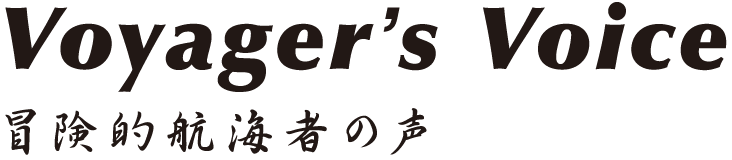I N T E R V I E W : D U K E K A N E K O
協力:Ocean Va’a Hayama 編集:Voyager’s Voice 企画・制作:Shonan Outrigger Canoe Club Corp.
南太平洋で生まれたアウトリガーカヌーには、数千年にわたる長い歴史に育まれた独自の文化と精神があります。タヒチやハワイで今もなお伝承されているそのスピリットこそ、アウトリガーカヌーの最も重要な要素だと金子デュークさんは言います。現在、自身が立ち上げたアウトリガーカヌークラブで日々葉山の海を漕ぎつつ、そのスピリットとカルチャーの普及に尽力している金子デュークさんに話を聞きました。

金子デューク Duke Kaneko
1963年長崎県出身、オーシャンヴァア副代表。’80年代のアメリカ西海岸でアウトリガーカヌーに出会い、2007年ホクレアの日本航海に接して、神奈川県葉山町に「オーシャンアウトリガーカヌークラブ(現、オーシャンヴァア)」を設立。オーシャンパドラーとして活動を続けるとともに、ポリネシアに古代から伝わるカヌーのスピリットと文化を伝えている。
葉山Ocean Va’a オーシャンヴァア
Kimokeo and Duke
https://www.paddleformotherearth.com/kimokeoandduke
サーフィンのために留学した’80年代のアメリカ西海岸カリフォルニアで初めてアウトリガーカヌーと出会う。今から35、36年前のことだった
──デュークさんのクラブ「オーシャンヴァア」の「ヴァア」とはどんな意味ですか?
ハワイをはじめ英語圏では「アウトリガーカヌー」という呼び方のほうが一般的なんですが、タヒチやハワイでカヌーの文化やスピリットを大事に漕いでいる人たちは、今でも敬意を込めてタヒチでは「ヴァア(Va’a)」、ハワイでは「ワァ(Wa’a)」と呼んでいます。
ポリネシアで古くから使われてきた呼び方で、「カヌー」であり「海に浮かぶ森の精霊が宿る木」という意味です。そこで僕らのクラブでも3、4年前に「オーシャンアウトリガーカヌークラブ」から「オーシャンヴァア」に名称を変えたんです。
──そんなヴァア(アウトリガーカヌー)との、そもそもの出会いを教えてください。
僕は幼い頃から海を身近に育ち、高校卒業後はサーフィンがやりたくてカリフォルニアの大学に留学したんです。当時、サーフィンといえばカリフォルニアという時代でした。最初に行ったのはノースサンディエゴですが、僕はサーフィンをしながら、波のない日はビーチを走ったり、トライアスロンのレースにも出ていたんですよ。
そして地元のサーファーたちは波のないときにアウトリガーカヌーを漕いでいた。そのチームに参加したのがカヌーとの最初の出会いです。僕が19か20歳くらいだったから37、38年前。’80年代の初頭ですね。
──当時のカリフォルニアではサーフィンやスケートボードのようにメジャーだったんですか?
いえいえ、いわゆるアメリカ西海岸のビーチカルチャーという感じではありませんでした。サーフィンやスケートと違って、アウトリガーカヌーって個人スポーツではないんですよ。まだ一人用カヌーもほとんどなかったですし、平日の夕方や週末にみんなで集まって、シックスマン(6人乗り)を漕ぐ。そうしたアウトリガーカヌークラブがカリフォルニア各地にできはじめた時期でした。
──デュークさんもクラブに所属したんですか?
学校の関係で、その後ニューポートビーチに移ったんですが、そこで「ニューポートアウトリガーカヌークラブ」というカヌークラブに所属しました。
1950年代にアウトリガーカヌーを初めてメインランドに持ち込んだ人たちが立ち上げた草分け的クラブです。メンバーはハワイ出身の人が多く、コーチは全員ハワイアン。そのなかでカラマさんという方に出会ったのが今の僕の始まりです。カラマさんの一族はハワイでも知られたウォーターマンファミリーで、サーフィンをやってる人ならご存じのデイブ・カラマという有名なビッグウェーブサーファーは、彼の甥っ子です。
──アメリカ西海岸にいて、カヌーを通してディープなハワイのカルチャーに触れた?
いや、当時の僕はまだ何も知らなかったし、単にスポーツ的にカヌーを漕いでいただけです。ただ、カラマさんたちからはカヌーカルチャーの話はよく聞かされていました。「ヴァアと呼ぶんだよ」とかね。今から思えば、彼らのほとんどが’70年代のホクレアのクルーだった。その出会いは僕にとって大きなものでしたね。

古代から伝わる天文航海術を頼りに
外洋航海カヌー「ホクレア」が日本に寄港
それによって大きく舵を切ったデュークさんの人生
デュークさんの言う「ホクレア」とは、古代ポリネシアの航海カヌーを再現した有名な外洋航海カヌーのこと。ハワイ人のルーツはタヒチにあることは解明されていましたが、問題はタヒチからハワイまで4400kmもの外洋を、小さな手彫りのカヌーで航海できたのかどうか。それを証明したのが「喜びの星(Hoku le’a)」と名付けられた「ホクレア」1976年の処女航海でした。
近代的な航法や機器を一切使うことなく、南太平洋に古代から伝わる天文航海術を頼りに、ハワイからタヒチまでの大海原を乗り越えた。それはハワイアンのルーツに迫る伝統文化復興運動を後押しし、ポリネシアやミクロネシア全域の住民にも大きな自信と誇りを与えたと言われています。
ホクレアはその後も南太平洋を中心に外洋航海を重ね、2007年にはハワイからミクロネシアの島々を経由して日本にやってきます。沖縄から奄美、九州、瀬戸内海の各地に寄港しながら横浜へ。このとき、デュークさんはホクレアを迎えるために、日本最初の寄港地、沖縄の糸満市へ足を運んだといいます。そのことが後のデュークさんの人生を大きく変えることになります。
──ホクレアが日本に航海した当時、デュークさんはどんな状況だったのですか?
茅ヶ崎に住みながらも、カリフォルニアとポートランド、ハワイにオフィスを持ち、子供服や古着、雑貨やサーフィン用品などの輸出入と販売を幅広く営んでいました。大学を終えて帰国し、結婚して子どもが生まれ、子育てのために家族でまたアメリカに戻り……帰国したのが2006年。日本にホクレアが来たのはその翌年。そのとき僕は44歳でした。
ホクレアって、コーチたちが話していたあのホクレアじゃないか! って。そこで勝手に歓迎委員会を名乗って、僕の出身地である長崎で講演会を始めたんです。長崎はハワイとのつながりが浅い土地でしたから、ホクレアとはどう貴重な船なのかということを伝え、歓迎する仲間を募るためにです。
──ずいぶん思い切った動きですね。
これはたいへんなことだと、仕事を置いてもやる価値があると感じましたから。沖縄でホクレアを迎えてからはクルーたちと仲良くなり、彼らが上陸してホテルや民宿に泊まっている間は、僕がホクレアの番をすることになったんです。「ウォッチ」という見張り役です。
それ以降、日本を航海する3カ月間はほとんどホクレアと行動を共にしました。家族も戸惑ったようです。今でもよく言われるんですが「家族とホクレア、どっちが大事なの!」となじる妻に対し、そのときの僕は「ホクレアだ」って答えたらしいです(笑)」
──デュークさんは、当時のホクレアクルーと面識があったのですか?
いえ、初対面です。ニューポートビーチのコーチたちとは年代も違っていましたからね。それでもすぐに仲良くなれたのは、やはり名前が「デューク」だったからじゃないでしょうか。なぜかというと、ハワイでデュークといえば「デューク・カハナモク」。ワイキキビーチに銅像が建つほどの英雄です。なので、それまではハワイの人に対して「デューク」と名乗ることすら抵抗があったほどです。
そのうえ偶然にも、カハナモクさんの甥っ子さんがそのときのホクレアのクルーにいたんです。それで「お〜い、みんな、日本のビジネスマンサーファーのデュークが来たぞ」ってことになって大いに盛り上がったんです。それからです。「じゃあデューク、俺たちが上陸している間、ホクレアを頼むな」ってことになったのは。
──それにしても、よく初対面のデュークさんに大事なホクレアの番を任せましたね。
経験を重ねたハワイアンは、形式よりも自分の直感を大事にしますよね。そのおかげだと思います。それにおそらく、僕の意気込みも相当なモノだったんでしょうね。当時40代でまだ若くて意欲も満々でしたしね。これはもう、人生のなかでそう何度もないようなことだから、しっかりとホクレアを学ばせてもらわなきゃ、という意欲がすごく強くて鼻息も荒かった。だから彼らも僕を受け入れてくれたし、あれこれ指示してくれたんだと思います。若いときにカラマさんと出会っていなければ、僕はこれほどまでにのめり込まなかったでしょうね。


絶頂だったビジネスとリッチな生活を投げ打ち
裸一貫で葉山にアウトリガーカヌークラブを開く
──葉山にアウトリガーカヌークラブを開いたのはなぜですか?
ホクレアが伝えようとしたことを、日本の大人や子どもたちに伝えなきゃ、と強く感じたからです。当時、ビジネスは絶好調。バブル時代だったから何でもよく売れたし、僕は茅ヶ崎に大きな家を建てて住んで外車を乗り回し、はたから見てもリッチな湘南スタイルの生活を味わっていたんです。そんなときにホクレアが日本に来た。なぜ、アメリカ本土やヨーロッパでもなく、日本だったのかと。日本からの移民がハワイを支えてきたからという理由は、表向きのものとしか僕には思えませんでした。そうではない、なにかの理由がきっとあったはずだと。
ホクレアが日本を離れた後も1年間くらい、その意味をずっと考えていたんです。仕事も手に付かなくなるくらいもんもんとしながら……。それで、ようやく気がついたんです。僕が影響を受けたカヌーやハワイのスピリットって、今の暮らしと真逆だよな。こんなことを続けていちゃだめだよなと。そこで会社を整理し、家を売って、葉山に移り住んだんです。
──またまた極端な転身ですね。
たしかに、生活はガラリと変わりましたね。いきなり会社を閉じて無職になるし、家は古いボロ家に引っ越しクルマも変わるし。家族は相当ショックだったみたいです。でも、息子たちは大学まで行かせたし、もう大丈夫だという思いはありました。それにホクレアが横浜を離れるときにクルーから言われた言葉が頭を離れなかったんです。「デューク、今回の日本航海は単なるイベントではないからな。これは始まりのはじまりなんだよ、ここからすべてが始まるんだよ」と。
──なるほど。それをご自身のカヌークラブで実現しようと考えたのですか?
その通りです。僕の役目はホクレアのスピリットを伝えることだと思い至ったのです。ヴァアは歴史あるハワイのカルチャーであり、精神性が大事だとは薄々気づいていたんですが、どちらかといえば、まだまだスポーツ的な部分が僕のなかにあった。それがホクレアとの出会いで一変させられたんです。
スピリットを伝えるといっても、日本にはホクレアのような遠洋航海ができる大型のヴァアはない。けれども、同じく古代から続く6人乗りのヴァアでその精神を受け継いで、カヌーで島々をつないで小笠原諸島まで漕いでいく。そうしたプロジェクトを立ち上げたんです。それが今の「オーシャンヴァア」というカヌークラブの始まりです。
──クラブの趣旨については、メンバーの皆さんにどう伝えているんですか?
ホクレアがあってこのクラブができたとお伝えしてます。そのスピリットは大切で、もちろん大会に出ることを目標にしたり、海に癒やされるために漕ぐというのものいいのですが、もともとのきっかけは大事にしていきたいし、それは続けなければと、ことあるごとに話をしています。
──なるほど。
でも、ヴァアのスピリットを現代社会のなかで伝えるのは簡単ではありませんね。みなさん平日は普通に東京の会社に通って働きながらストレスを抱え、それを週末の海で発散したり、癒やされたりしたりしたいじゃないですか。そんな大人に対して、海に祈りを捧げましょうと言ってもなかなか伝わるものではない。それでもカヌークラブで漕ぐ以上、海への感謝や仲間と協調する精神がなかったら、カヌーは楽しめないと思います。
僕がよく言うのは、カヌークラブは昔の島の生き方そのものだと。絶海の孤島で暮らしていくには、みんなで協力して、やらなきゃいけないことをやり、恵みはみんなで分け合う。それがヴァアのスピリットの根底にあるわけです。実際、カヌーを漕ぐときに気持ちをひとつにすることがとても重要で、仲間に対してネガティブな感情を抱いたり、少しでも疑問に思ったりする部分があれば、カヌーは失速しますからね。常に信頼関係で結ばれていなければ、遠くまで漕ぐことはできません。

祈りを捧げて海に出て、ただただ気持ちを込めて漕ぐ
そんな精神はなぜ重要だと考えるのか
──デュークさんの葉山での日常を教えてください。
極力、毎日海に出てカヌーを漕ぐことを日課にしています。お坊さんのお務めと同じで、漕ぐことは木魚を叩くことと同じです。スマホなどの現代に機器に囲まれて生きる僕たちは、とにかく海に出ないとなにも始まらないんです。
僕らには古代人のように海に出るだけでいろいろなことを感じる能力はありませんが、僕はそれにすごく憧れます。春、秋、冬は日中の時間、夏は早朝と夕方の静けさがある時間を選んで、なるべく長く海に出る。もちろん、そこでインターバルをやるとかではなく、ただただ、気持ちを込めて海と語り合うように長い時間漕ぐだけです。
──毎日同じ景色の海を漕いでいて飽きませんか?
まったくないです。たぶん、僕はそういう目線で見ていないのだと思います。もちろん、どこかを目指そうということはあっても、景色というよりは、常に目の前の海と向き合っているからかな。海は毎日違うし、進むたびに変化し続けます。風の向きも強さも、潮の流れもすべて違う。その変化が楽しいんですね。
──海に出るときは、なにか特別なことはしますか?
僕らがよくやるのは海に向かっての祈りです。朝なら、東の空から昇る太陽に向かって祈りを捧げる。子どもたちにもやらせています。最初のころはみんな嫌がっていても、しばらくすると僕がいなくても、海に出るときは自然にやるようになっています。やらないと海に出られない、という意識になっていくんですね。
──いい意味で、意識化と習慣化ができている。
そうなんです。ぱっとパドルを抱えて安易に海と陸の境界線をまたいじゃダメだよ、と僕はよく言ってます。必ずなにかしら、感謝の気持ちを唱えてから海に出る。なんならカタチだけでもいいんです。でも、そうした儀式すら恥ずかしくてできない人は、必ず間にワンクッション置いて、陸のことは陸に置いてから海に出ましょうと。
大人でも同じです。カヌーを出すときもおしゃべりしながらではなく、ちょっと謙虚な気持ちになって、神輿を担ぐようにみんなの気持ちをひとつにして、ヴァアを海に浮かべる。そういうことは欠かさずやっています。そういう意識は大切だと思うんですよね。
──意識のスイッチを切り替えるわけですね?
その通りです。それは本当に必要なことだと思います。今はエンジン付きの船で、誰でも簡単に海に出られるけど、昔は海に出るという行為それ自体がひと苦労だった。そういう時代が何千年も何万年もの間続いていたわけで、もともと海はそういう時代のほうがはるかに長かったわけです。そうした意識で海に対して謙虚な気持ちを持つことは、安全という部分に直結するし、神聖な場所に土足で踏み入れない的な感覚によって、海の環境を守るという気持ちも自然と育まれると思うんですよね。
また、その意味ではヴァアは極めて簡素な乗り物で、形状もリギング(ロープで組み立てる方法)も古代の頃とさほど変わらない、パドルで漕ぐという行為も、数千年、数万年前の人間が日常的にしていたことと何も変わらないのです。当然ですが、エンジンも化石燃料も使わない。究極にシンプルで、海に優しい持続可能な乗り物。それが私達の漕いでいるヴァアなんです。


100年先を見据えながら、子どもたちに未来の海を託す
それを自分の使命だと捉えているデュークさん
──子どもたち向けのプログラムはどんな内容ですか?
基本的に小学生向けで4月から11月をメインに、平日の放課後や週末に活動しています。以前はクラブメンバーの子どもが多かったんですが、このコロナで学校が長いお休みだったこともあって、人数は倍くらいに増えました。入会前には必ず親とは面接するのですが、海と自然に対して意識の高い親御さんが多く、僕が言ってるようなことも理解していただける方が多いです。葉山はそういう人たちが集まっている土地なんだなとあらためて思いましたね。
──子どもたちになにを伝えたいと考えますか。
子どもたちは宝です。吸収力も高いし、集中力もある。彼らには、単に知識や情報を得ようとするのではなく、「野生に帰ろう」「海を感じよう」ということを伝えたいですね。彼らがこれからの地球を担っていく存在ですから、力を抜けません。彼ら子どもたちの意識が変われば、地球の環境ももっとよくなるはず。今だって、自分たちの若い頃にくらべれば海や川はきれいになったし、ずいぶんよくなってきているじゃないですか。
それが子どもたちだけではなく、彼らの子どもの代まで含めて考えれば、僕たちは100年先を意識して教えることになります。そうなれば、人間の感覚も意識もかなり変わっていると思います。彼らが当然のように海に感謝し、地球のなかでは海も人も同じ生命体なのだと感じてくれるようになれば、100年後の海と自然環境は大きく変わるはずです。将来は明るいと思いますよ。
──今後のデュークさんの予定は?
今年からクラブの代表を息子に交代しています。今までと同様にクラブの活動は続けますが、ほかにもいくつかプロジェクトを準備中です。ひとつは「パドルフォーザマザーアース」と題した被爆地広島から長崎までを漕いでつなぐボヤージングです。当初はヒロシマとナガサキという世界でも知られた平和の象徴を結んで、世界中のパドラーで漕ぎつなげる計画でしたが、コロナによって延期になり、現在は状況を見守っている段階です。
これもコロナで延期になってしまったのですが、ハワイ州観光局が後援についてハワイのスピリットとカルチャーを伝えるイベントを開催予定でした。
肝心のハワイからスピーカーが来られなくなってしまったので延期ですね。また、ホクレアが世界一周したときの記録映画があるのですが、その待望の日本語翻訳版が完成したので、パタゴニアさんに協力いただき全国各地で上映会を開く予定です。
──やること満載ですね。
ホクレアと出会って人生が大きく変わったのは44歳のときでした。それ以降、僕は全くブレていないつもりです。ホクレア、そして海の神様カナロアとの誓いと覚悟は、消えること無く僕の両肩と脚のTatooに刻まれています。そしてそれは死ぬまでそれは消えることはないでしょう。だからこそ、ヴァアを漕ぐことのコアな部分を今後も伝えていけたらと。それは僕の、ハワイ語で「クレアナ」というのですが、この地球に生を授かった使命だと思っています。



協力:Ocean Va’a H ayama 編集:Voyager’s Voice 企画・制作:Shonan Outrig ger Canoe Club C orp.